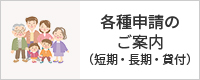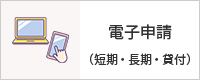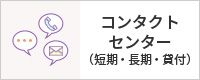本文
外来療養に係る高額療養費の現物給付化
平成24年4月1日から、医療機関等の窓口での一時的な負担を軽減するため、外来に係る高額療養費についても現物給付方式での支給がはじまりました。
70歳以上の方については、入院に係る医療費の場合と同様に、高齢受給者証を医療機関等に提示することにより現物給付方式による支給が受けられます。
70歳未満の方が現物給付方式による高額療養費の支給を受けるためには、マイナ保険証の提示等によるオンライン資格確認での情報提供に同意していただくか、組合員の方の所得区分を記載した「限度額適用認定証」を病院に提示する必要があります。限度額適用認定証の交付を受けるには、支部での申請手続きが必要となります。
※ 指定訪問看護に係る療養についても同様の扱いとなります。
※ 現物給付方式による支給を受けない場合は、従来どおりの償還払い(現金給付)方式による支給となります。
(1)月の途中で現物給付方式による高額療養費の支給を受ける場合
(高額療養費算定基準額の区分が「標準報酬の月額28万円~50万円」の事務官等)
<計算例1>
4月1日:A医療機関で外来診療<医療費100,000円、自己負担額30,000円>
4月16日:オンライン資格確認での情報提供に同意または限度額適用認定証を提示し、A医療機関で外来診療<医療費300,000円>
自己負担限度額:80,100円+(100,000円+300,000円-267,000円)×0.01=81,430円
この場合、月の初めにさかのぼって適用されるため、4月16日の窓口での支払いは、81,430円-30,000円(4月1日支払い分)=51,430円でよいことになります。
<計算例2>
4月1日:A医療機関で外来診療<医療費300,000円、自己負担額90,000円>
4月16日:オンライン資格確認での情報提供に同意または限度額適用認定証を提示し、A医療機関で外来診療<医療費100,000円>
自己負担限度額:80,100円+(300,000円+100,000円-267,000円)×0.01=81,430円
この場合、4月1日に自己負担額として90,000円を支払っているため、4月16日の窓口での支払いは必要ありません。なお、すでに支払った分と自己負担限度額との差額、90,000円-81,430円=8,570円は医療機関から払い戻されることになります。
(2)同一の月に複数の医療機関等を受診した場合
(高額療養費算定基準額の区分が「標準報酬の月額28万円~50万円」の事務官等)
<計算例>
A病院(外来1回目):<医療費100,000円、自己負担額30,000円>
B薬局 :<医療費200,000円、自己負担額60,000円>
A病院(外来2回目):<医療費300,000円、自己負担額90,000円>
この場合、複数の医療機関同士では合算することができないため、B薬局では自己負担額である60,000円を支払う必要があります。A病院については、2件の医療費は合算することができるため、自己負担限度額は80,100円+(100,000円+300,000円-267,000円)×0.01=81,430円となり、81,430円-30,000円(1回目支払い分)=51,430円を2回目の外来の際、窓口で支払えばよいことになります。
なお、別途高額療養費の申請を行うことにより、B薬局での自己負担額を合算した高額療養費の支給を受けることができます。
(3)同一の月に同一の医療機関等で入院と外来受診をした場合
(高額療養費算定基準額の区分が「標準報酬の月額28万円~50万円」の事務官等
<計算例>
A病院(入院):<医療費400,000円、自己負担額120,000円>
A病院(外来):<医療費300,000円、自己負担額90,000円>
この場合、入院と外来は別々に扱うことになるため、入院については、自己負担限度額が80,100円+(400,000円-267,000円)×0.01=81,430円、外来については、自己負担限度額が80,100円+(300,000円-267,000円)×0.01=80,430円となり、それぞれの金額を窓口で支払えばよいことになります。
また、この場合、2件の医療費は合算の対象となるため、後日、共済組合に申請を行うことにより、差額分の高額療養費の支給を受けることができます。